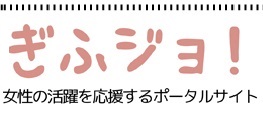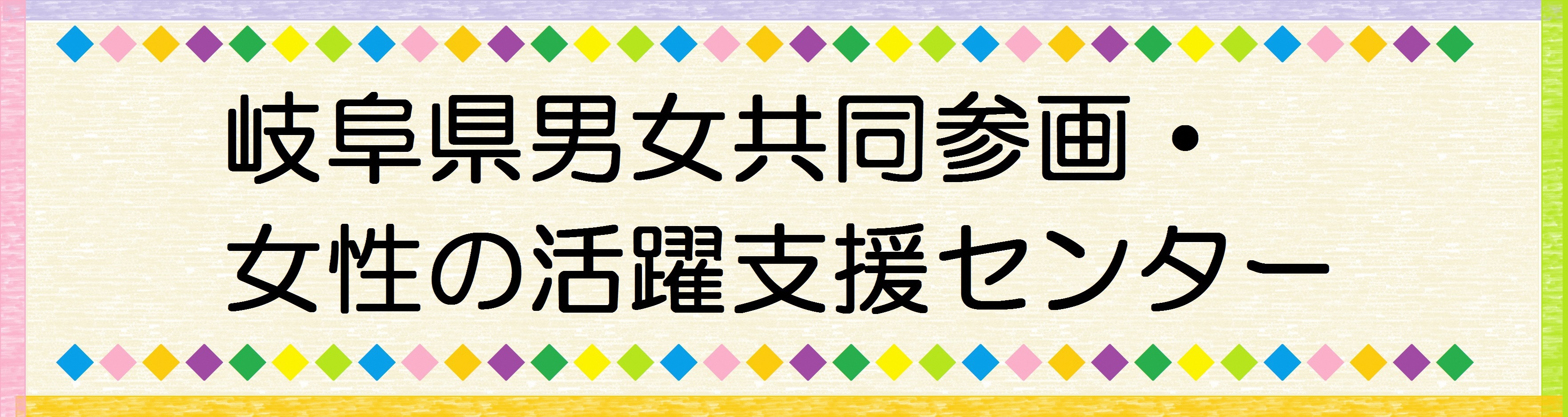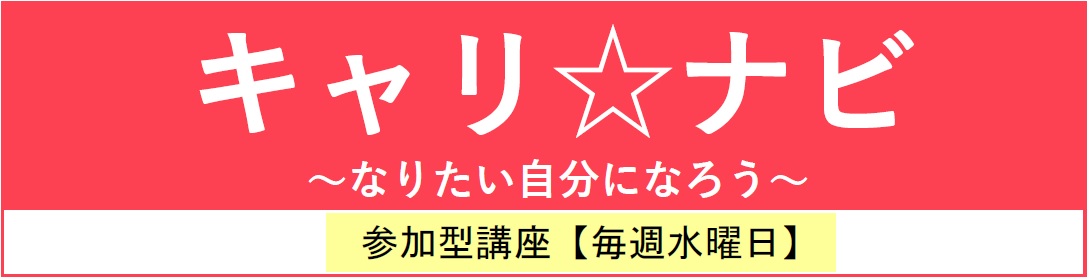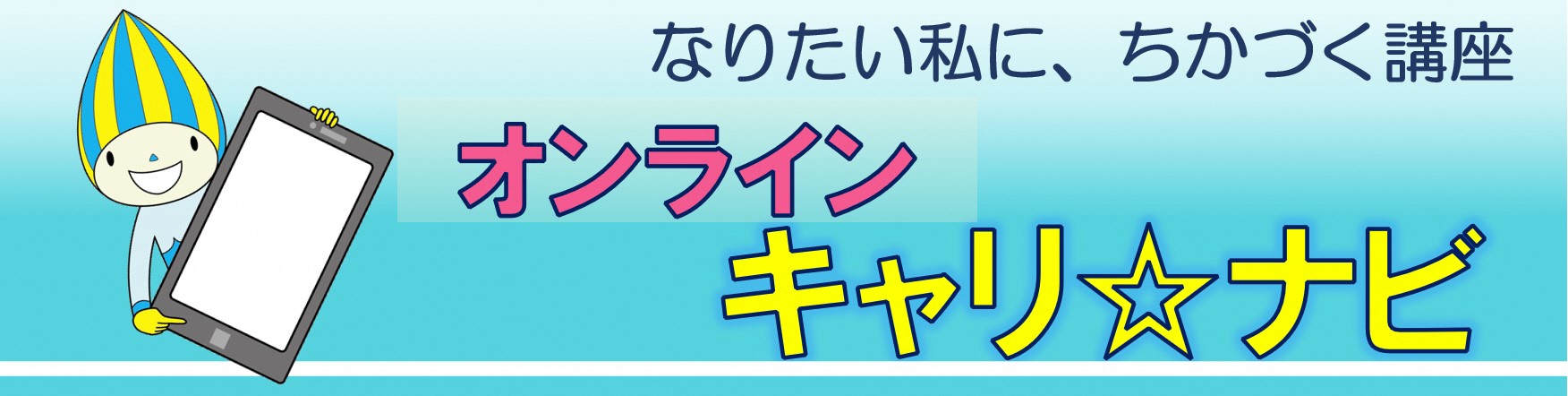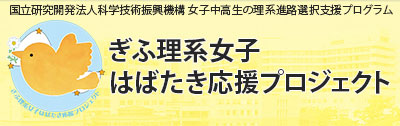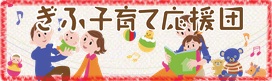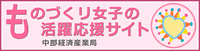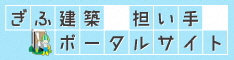可児市の株式会社サーバントは、未就学児や小中高生から18歳以上の成人まで、幅広い年齢の障がいのある人たちを対象に、児童発達支援や放課後等デイサービスから就労支援まで様々な支援を提供している。また、この会社では社員に対する支援にも力を入れており、会社の費用負担でBBQなど社内イベントの開催はもちろん、部活動を立ち上げて大会への出場も積極的に行っている。職員は女性の比率が高く年齢構成でも若い人が多いため、子育て世代に対する支援は制度の充実を図ると同時に、個々の事情に応じた柔軟な対応で離職を防ぎ、充実した福利厚生と合わせて定着率の向上につなげている。
優良取組事例

個々の事情に合わせて
柔軟な働き方を可能にする
臨機応変な対応で
制度のスキマを埋めています
株式会社サーバント/可児市
物心両面の充実が大切
「福祉系の会社のため女性の割合が多く、その中でも20代から30代の若い女性が多い年齢構成となっています。」広報課長の佐々木明人さんは自社の社員構成をそう説明する。若い女性が多いということは結婚・出産・育児と仕事の両立に悩みを抱える世代が多いことを意味する。一般企業なら定年となる年齢を超えて仕事を続ける職員や、夫婦や親子で勤めている家族もあるなど、多様な働き方ができる会社と言えるだろう。就業規則や福利厚生などに関しても法令を遵守することは勿論だが、個々の状況や背景にも目を向け、制度が想定していない対応も柔軟に行っている。これは社長の考え方を色濃く反映しているからだが、事業規模も社員数も大きくなってきた昨今では、過去の事例も反映させてより細かな対応が可能な制度への改修を進めている。
人財を最大限に生かす
人事面においては「働きたい人を拒む理由は無い」という考えから、資格の有無や年齢に制限を設ける事は無く、障がいのある人も受け入れている。また、適格と判断すれば女性の管理職昇格も積極的に行っている。
系列の施設「天空の牧場 スクーデリアステラ」の管理者を務める松富有紀さんは、ホースセラピーを取り入れた「放課後等デイサービス サーバントホース」の立ち上げから参加してきたスタッフで、馬に関する知識・技術・経験からセラピー参加者や馬主への対応などの実績と、スタッフ育成も含めた全てを安心して任せられる能力があると会社が判断し、管理職として新施設の運営を任されている。「今はパートも含めて6人ほどのスタッフを指導しながら、一般向けの乗馬体験やスクールも開講しています。また、来年にはこの牧場で障がい者の就労移行支援にも取り組む予定です。」と語る松富さんは、会社の立ち上げた部活動の1つ「ゴルフ部」の部長も務めています。企業対抗レディーストーナメントに出場して上位入賞を果たすなど活躍していますが、部活動で得た知識や経験を業務に落とし込めないか模索中だとも話してくれました。
誰もが制度を活かせるように
産休・育休に関わる制度では金銭の補助が手厚く行われています。産休から復帰後は時短勤務を選択する(或いは選択せざるを得ない)ケースが多いと思われますが、時短勤務中もフルタイムで勤務していた頃と同額の給与が支給されます。これは出産後に中途入社した職員にも適用されますし、他には保育料の半額補助も行っています。これらの補助を受けている「児童発達支援 虹色パーク」に勤務する児童指導員の和田知世さんは「友人に話すと当然ながら羨ましがられます。収入が減らないのは安心感につながりますし、生活に不安が生じないのは仕事にも良い方向で影響していると思います。」と話してくれました。
他にも半日単位で取得できる看護休暇など会社は様々な制度の充実に努めていますが、「時短勤務は同僚に迷惑をかける」などの負い目を感じることなく制度が利用できる風土を作ること、様々なケースへの柔軟な対応で制度の網からこぼれ落ちることが無いよう配慮することなど、小さな会社だからこそできる小回りの利いた対応を続けています。
職員の安心が利用者の幸せを生む
職員がお金の面や生活の面で困らないようにすること、それを社長が大切だと考えるのは、この会社が障がいのある人に手を差し伸べる仕事をしているからです。不安を抱えた職員が人を安心させることはできません。利用者により良い支援を提供するためには、職員が安心して働き続けられるワークライフバランスの優れた会社であることが必要なのです。組織がどんどん大きくなれば個人経営のような小回りは難しくなるかも知れませんが、その思想は社風に反映され生き続けるでしょう。