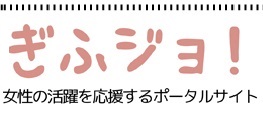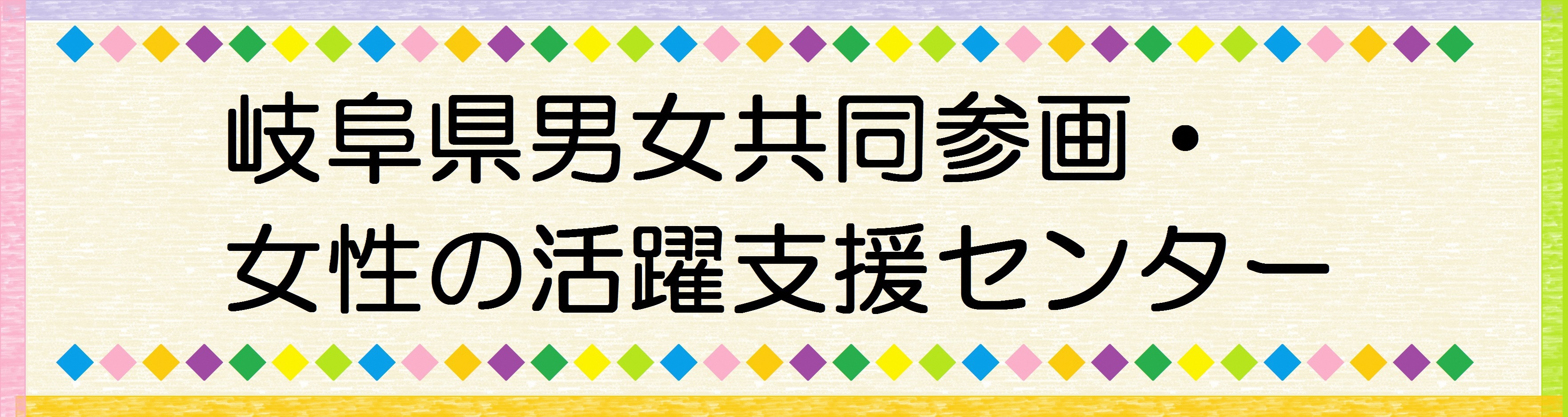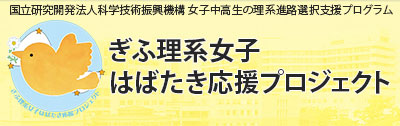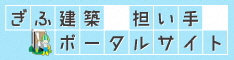産前・産後の女性の健やかな体と心をつくる、ヘルスケアプログラムの普及に取り組んでいる認定NPO法人「マドレボニータ」。その認定インストラクターとして、山本裕子さんは岐阜市で「産後ケア教室」を運営し、母となった女性が心身ともに健やかに人生を送れるようサポートしています。
産後の心身の不調が改善したことをきっかけに今度は伝える側になろうと
長女を出産後、体調を崩してしまい、2度の流産を経験。また夫婦関係もこじれるという、辛い時期を2年間ほど送りました。子どもを可愛く思えなくなったことが衝撃でしたし、夫にも嫌悪感を抱いてしまい、心身ともにボロボロの状態でした。
このままではいけないと思い始めたとき、テレビで「マドレボニータ」を知りました。ホームページやブログを読み、これは今の自分に必要だと思ったのです。岐阜には「産後ケア教室」がなかったので、名古屋まで通いました。
当時、子どもをいろんな場所に連れ回し、グズったらお菓子などを与えて、自分は友だちとおしゃべりを楽しむということも多々あったのですが、マドレボニータからは「子どもにとってそれは幸せなのかな?」と言葉を投げ掛けられました。「小さなうちから、ひとりの人間として扱ってあげる。子どもの居場所、自由に過ごせる場所を作っていくのも大人の役目だよ」と言われ、とても考えさせられました。
週1回、全4回のプログラムでしたが、受けてみたら、自分の体が元気になっていくのがわかるのです。子どもも可愛いと思えるようになって、育児も楽しめるように。夫ともやり直そうと思えて、関係を修復するためにちゃんと向き合い始めました。
同時に、この教室は必要なもの、と思いました。岐阜に教室がないなら自分が伝える側になりたい、と考えたのがスタートです。勉強できる環境を整えるため、初めて託児を依頼し、研修を受けて、2010年に産後セルフケアインストラクターの資格を取得しました。
体力と言葉を取り戻すために教室で体のリハビリと対話を
産後ケア教室は1回2時間のプログラムです。前半はバランスボールを使った有酸素運動で、しっかり負荷を掛けて、体力をつけていきます。妊娠中に限らず、運動不足の方も多く、初回はヘロヘロになりますが、最後には息切れもしなくなります。
後半はシェアリングを行います。これは対話の時間です。赤ちゃんを持つと、赤ちゃんを主語に話すようになって、自分のことを語る言葉が錆びついてきます。マドレボニータでは「言葉を失う」と言っています。その言葉を取り戻すためのワークであり、これからの人生を考え、見つめ直していきます。
最後がセルフケアです。4回でプログラムが終了しますので、卒業後もご自宅で体を整えられるように、簡単なエクササイズをお伝えします。
産後ケア教室は、この3本柱が基本となります。現在は岐阜で2教室、桑名で1教室を運営しているほか、昨年5月からはオンラインでの教室も始めました。不定期ですが、妊婦と産後女性が語り合うサロンや、妊娠中の夫婦を対象とした講座なども開いています。
公私の区別をあまりしないのが私にとって両立のコツ
シェアリングでは人生観や夫婦間のことなど、かなり踏み込んだ話もしますので、とても距離が近くなります。深い話ができる人と出会える、それがこの仕事の魅力です。10年前に卒業した母たちと未だに飲み友だちなんです。みんな子どもが大きくなって、ステージが変わっていく中、それを話せる関係性が築けているのが楽しいです。
夫や子どもたちには私の仕事を見せていますし、知ってもらっています。友人たちも同様です。あまり仕事だから、プライベートだから、と分けていません。週末の仕事、泊まりでの仕事や研修も、夫や実家の両親、そして友人に子どもを見てもらいながら、続けてこられました。本当に感謝しています。
そして、私の人生になくてはならないものと言えばMr. Childrenです。17歳から25年間、ライブには欠かさず出掛けています。彼らの音楽を浴びるように聴くのが大好きです。歌詞に励まされることが多くて、『GIFT』という曲の「白と黒のその間に無限の色が広がっている」も好きな言葉で心に残っています。
団体の共同代表に就任し新たな仕事に携わっていくことに
昨年の12月、マドレボニータの共同代表に就きました。団体としても大きな変化のタイミングと重なり、手を挙げました。インストラクターになって10年。今までは現場で、東海地方に産後ケアを広めることに注力してきました。43歳になって、この先の10年を見据えたときに、ここからは団体の中に入り、実務や後進の育成など団体全体の運営を担っていきたいと思ったのです。「全ての家族に産後ケアを!」という思いを持つ全国のインストラクター仲間と、もっと密にコミュニケーションを取っていける仕組みを作りながら、それぞれの力を発揮しあえる団体を目指していきたいです。また、産後ケアの認知度はあがってきましたが、その必要性をしっかり伝えきれていないもどかしさを感じていて、その課題についても取り組んでいければと考えています。