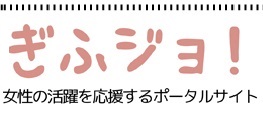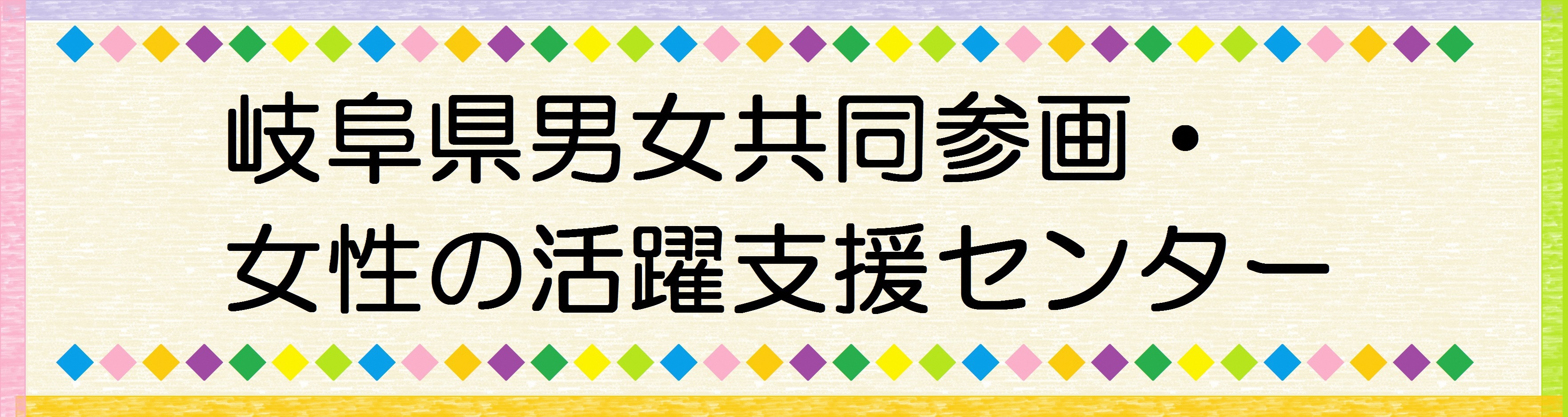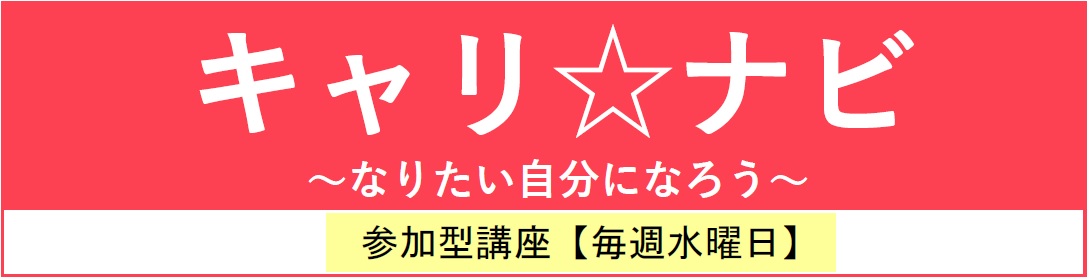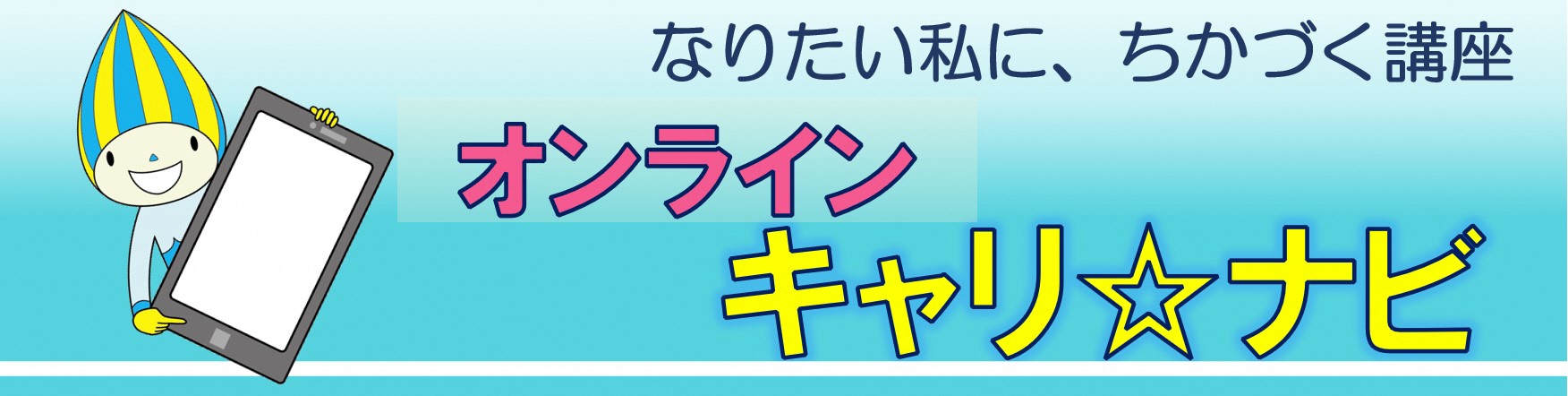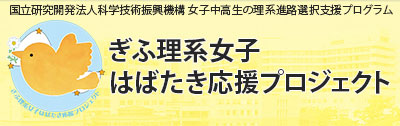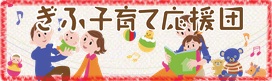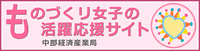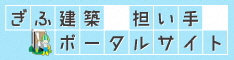障がい者が共同で生活する施設の所長を務めている辻野美紀さんは、若いころに取得したヘルパー2級の資格と人のためになる仕事をやってみようという気持ちを持って、未経験の介護・福祉の世界に飛び込みました。
未知への挑戦
子どもが生まれてパートの仕事を探していたとき、知人から募集が出ていると紹介された医療法人慶睦会の入浴介助専従のパートに応募しました。若い頃介護に興味がありヘルパー2級の資格を取りましたが、実務経験はありませんでした。小さい頃から、おじいちゃんやおばあちゃんと話をするのが好きだったことと、せっかく勤めるなら人のためになる介護の仕事をやってみようと考えたのが応募した理由です。
勤務し始めて数か月たったころ、認知症の方の介護に力を入れたデイサービスを立ち上げることになり、そちらに異動となりました。時間に合わせて決められたサービスを提供し、夕方になったら利用者さんに帰ってもらうのが普通ですが、そこの施設長と理事長の両方から「責任は持つから自由にやって良いよ」と言われ、自分なりに考えたことを実行してみました。こうすれば認知症の利用者さんがもっと自立に向けた生活ができるんじゃないかと考えたことを利用者さんのご家族と相談しながら実際にやってみて、症状が徐々に良くなってきたときに大きなやりがいを感じました。こんなに自分の思いを自由に形にできる職場は他に無いと思い、どんどん仲間と一緒に考えて提案すると同時に、介護福祉士やサービス管理責任者などの国家資格を取得し研修にも数多く参加しました。
ここは地域に密着した施設であるため、色々な人との繋がりが大事になります。周辺の企業に名刺を持って訪問し繋がりを広げるとともに、異業種からも良い点はどんどん吸収していくように努めました。
共に生きる
その後、高齢者と障がい者の共生型施設「千手の華」を立ち上げることになり、統括施設長をやらないかと打診を受けました。障がいの知識がない自分にできるのかと不安もありましたが、理事長の「任せる」との言葉で引き受けることにしました。始めは主に高齢者の方が利用されていましたが、徐々に障がい者の方も増えてきました。今まで介護の勉強はたくさんしてきましたが、障がいについての知識が全く足りていないため、これからの共生社会のためにも障がいの勉強がしたいと思い、障がいのサービスを幅広く行っている他施設で勉強させてもらいました。
「千手の華」の施設長時代には学童保育と子ども食堂も行っていました。スタッフ一人ひとりと面談を行い、その人の強みを探しスキルを上げていく、そんなことを繰り返しました。人は人との関わり方によって変わっていくものです。人を否定はしたくありません。マイナスから人を見るのではなく、プラスから人を見るよう心掛けていますが、一人ひとり本当に個性が違うので、どうしたら自分の思いが伝わり相手の思いを受け止められるか、難しい問題だと感じています。
人生に寄り添う
40代でこの事業団に移りました。利用者は日中仕事に出て夕方に帰ってくるという施設で、共に日常生活(食事・掃除・洗濯など)を送ったり、相談にのったりしています。利用者が仕事に行っている昼間は事務処理や会議のほか就労先を訪問したり、言葉の理解が難しい利用者のため書類を書いたり手続きのために病院や市役所へ一緒に行ったりしています。基本的には日勤の仕事ですが、緊急対応で夜間に駆け付けることもあります。
施設の利用者は知的障がいのある20~40代の方が中心です。以前は高齢者のお世話で人生の最後の部分に携わることが多かったのですが、ここでは若い人たちのこれから歩む人生に携わっています。知的障がいの方はこちらの言うことを素直に受け入れてしまうので、出来ないという先入観で否定から入らずに、色々な事を経験してほしい、成功しても失敗しても本人の自己決定を尊重していきたいと思っています。
続けることが大事
私がこの世界に飛び込んだ時はまだ赤ちゃんだった娘も、今は中学二年生になりました。娘が産まれた当時は子連れ出勤をしたこともありますし、少し大きくなってからは機会があれば職場見学もさせました。私が働く姿を見て育ったからでしょうか、将来は介護福祉系の仕事に就きたいと言っています。私はフルタイムで働くシングルマザーなので、娘の勉強や生活は自己責任でやらせています。やりたいことは制限しないで何でもやらせたいと思っているので、平日は習い事、週末は部活と大忙しですが、その送り迎えなどで出来る限り娘と関わるようにしています。休日でお互い時間が取れたときは一緒に買い物へ行ったり、私が好きなイルカを見に水族館へ足を延ばしたり、親子関係は良好だと思います。
私の好きな言葉は「継続は力なり」です。学び続け、考え続け、そして常に進化していく。私はそうしてきたつもりですし、娘にもそうしてほしいと願っています。