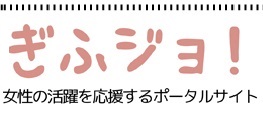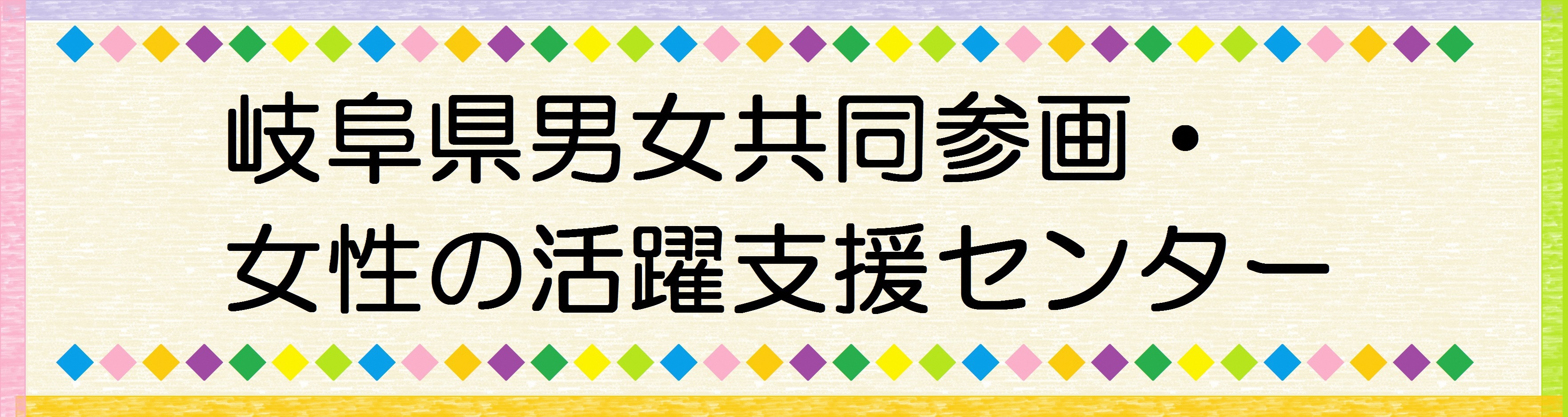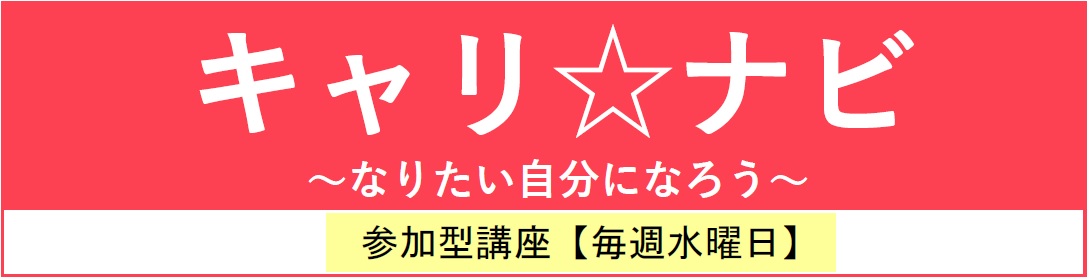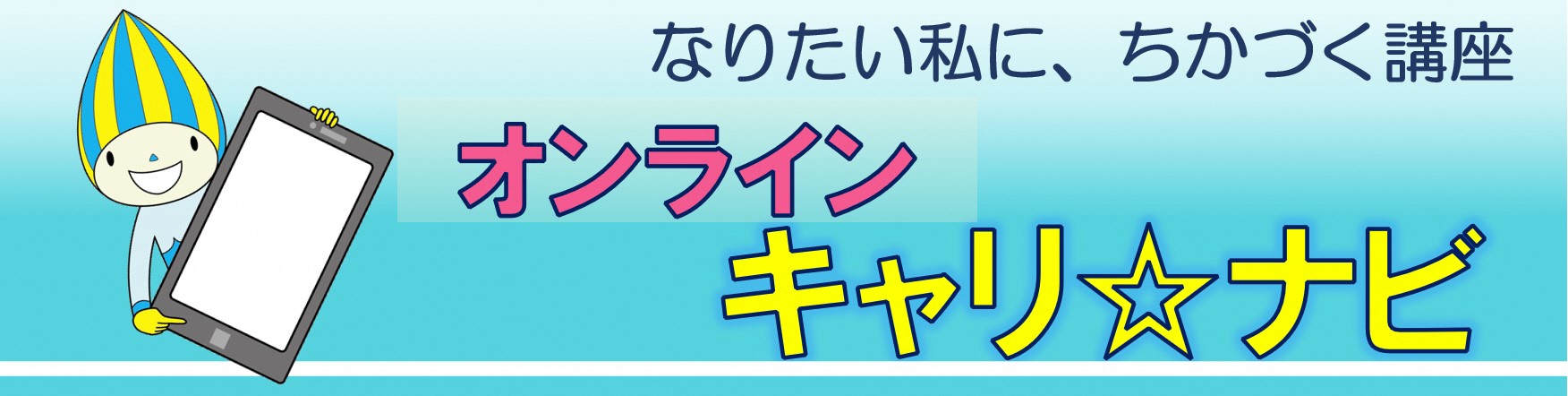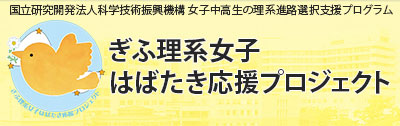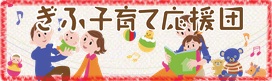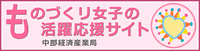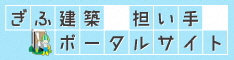恵那市三郷町の高台で農園を営む阿部真奈美さん。夏はトマト、冬はいちご、農閑期にはネギを栽培しており、いちごの最盛期には観光農園として、いちご狩りや直売も行っています。5人の子どもをもつ母で、子どもの一人に障害があることから、農業と福祉を組み合わせた農福連携も視野に入れつつ、楽しい農業を目指しています。
農業に面白さを感じて
最初の子どもを出産して子育てをしているとき、近所のトマト農家の方から、手伝ってほしいと声をかけられたのが、農業との出会いです。それまではアパレル関係の仕事をして、農業に携わるのは初めてでしたが、風が気持ち良いし、手をかけただけトマトが育っていくことを面白く感じました。
1年後、その方が高齢のため引退する際に「どうぞ使ってください」という言葉をいただき、ハウスや畑をお借りしてやってみることにしました。当初は自分ひとりでやれる規模で十分、ちょっとしたお小遣い稼ぎの感覚で、農業に取り組み始めたのです。
なにしろノルマはないし、人間関係の煩わしさもありません。私一人で完結できて、だれにも迷惑をかけない。その点が気楽だなと思っていました。
現在のように、規模を拡大して雇用型に切り替えたのは、一番下の子どもが障害を持って生まれてきたのがきっかけです。当時は障害者が自立できる場は今ほどなく、将来に不安を覚えました。自分にできることはないかと考えていく中、農業と福祉は相性が良いのでは、という思いに至りました。阿部農園が障害のある人たちの働ける場になれればと、生産規模を拡大していき、トマトに加えて、いちご栽培も始めました。
また、10年ほど前からは農閑期に露地栽培でネギを作って、学校給食用に出荷しています。トマトやいちごの加工品にも取り組んでいます。今はすべて委託ですので、自社加工場を持つのも目標のひとつです。
労働力の確保が課題
直売所へ買いに来てくれるお客さんから、「ここのは美味しい」という言葉を聞くたび「よっしゃあ!」と心の中で声を上げますが、そこで満足せず、もっともっと美味しいを極めていきたいと思っています。奥が深く、農福連携や6次産業化など、いろいろとチャレンジできるのが農業の魅力であり、楽しさだと思います。常に天気や気温、作物の状態などを確かめながら手をかけるのが面白く、いろいろと工夫を凝らすのも楽しいです。
できるだけ農薬などを使わないように、とは思っているものの、病気で全滅させてしまったこともあって、栽培の状況をみながら適時消毒をしています。消毒に変わる何かがあれば取り入れていき、無農薬に近づいていければいいなと思います。
私を含めて従業員、パートさんには作物の病気に対する危機意識を持ってもらい、安定栽培を目指しています。そのためには、どれだけ手をかけるかにもよりますが、やはり人手は必要です。やみくもに人を入れれば良いわけではなく、一人ひとりが長く勤めてもらえるようにしたいと考えています。季節雇用だと人が入れ替わってしまい、なかなか効率化が図れません。年間雇用にすると、農閑期と収穫期、緩急があるので、どうしたら一定化できるかが、大きな課題となっています。
農業だからこその両立
農業の場合、公私の切り替えがあやふやで、自分の段取り次第で働けるというメリットがあります。仕事中に「ちょっと授業参観の1時間だけ抜けてくるね」とか「子どもが駅まで送ってほしいと頼むので30分抜けるね」となっても、成り立つ仕事です。
多少なりとも時間に融通が効く仕事ですので、農業は家事や子育てとの両立がしやすいと感じています。子どもがまだ赤ちゃんだったときには、ハウスの中にベビーベッドを持ってきて、その傍らで農作業をしていました。
現在、私の母、夫、長女、次女、三女、長男、次男との8人暮らしです。農業は家業というイメージが強いですが、うちの家族は「これは私(真奈美)の仕事」と思ってくれています。夫もそういう認識のもと、共働きという形で、家事は折半してやってくれています。夫が早く帰ってきたら、食事を作ってくれたり、家のことをやってくれていたりするので、私が収穫期ですごく忙しいときなど、本当に助かっています。
質の向上と安定経営を
以前は一人でしたが、今は従業員やパートさんがいて、みんなで意見を出し合いながら農園をつくっていくのが、すごく楽しいと感じています。そのうえで、通年の労働力確保という課題のクリアに向けて、栽培規模を拡大し、農園の質を高め、障害者雇用も意識しながら、楽しく安定経営できるよう目指していきたいです。
まだ手をつけていませんが、耕作放棄地の活用も考えていきたいと思っています。形が悪かったり、耕作放棄地になるだけの理由があったりと、取り残されてしまいがちな農地が多くあります。そんな社会課題にも、今後貢献していければと考えています。
自分がやれると思っている間は、あまり後継者のことは考えていませんが、いずれ子どもが継ぎたいと思えるように経営環境を整えていきたいと思っています。まだ課題も多くありますので、それらを解決して、やりたいなと思ってもらえるような形にしたいです。