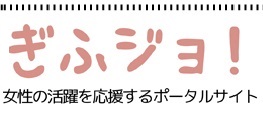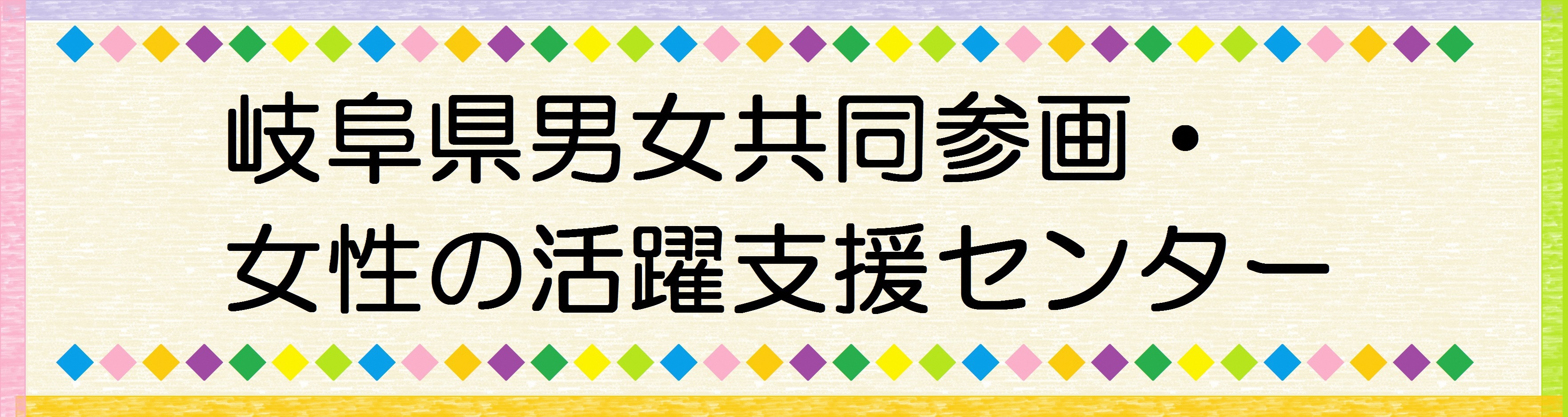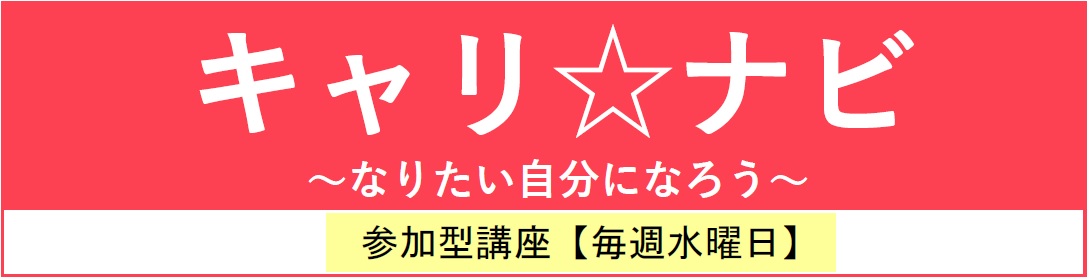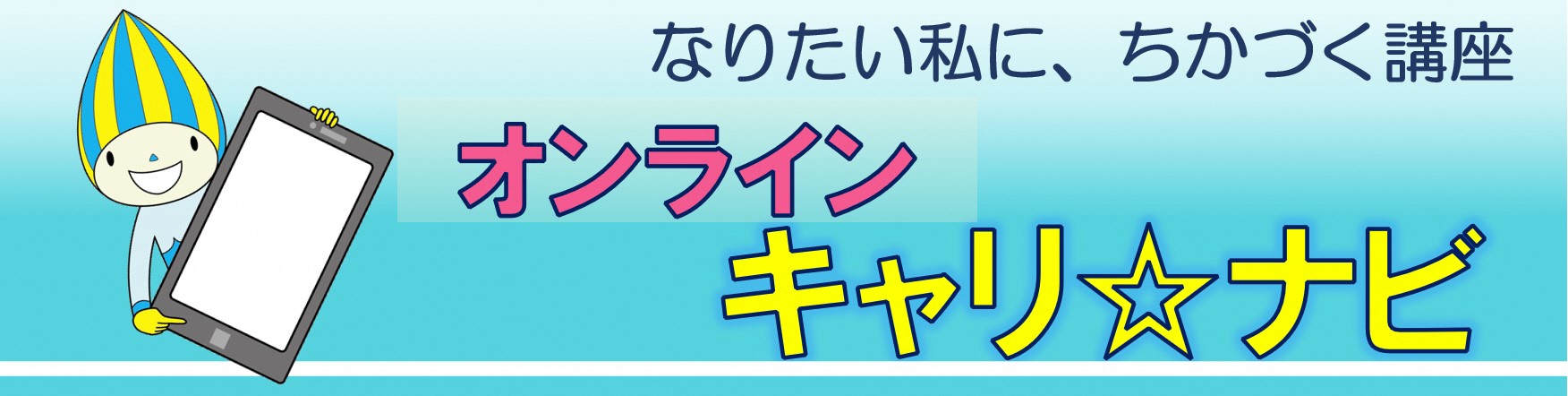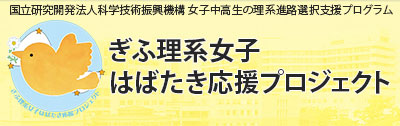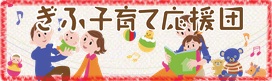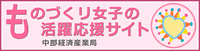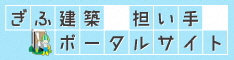川尻富士子さんは岐阜県高山市の専業農家に嫁いで40年。ほうれん草、トマト、米などを生産しながら、農閑期にできる活動をと、地域の仲間と一緒に農産物加工グループ「飛騨高山うるっこ」を立ち上げ活動してきました。また、販路を拡大するため、地域の他団体と一緒に「ひだあねさの会」を立ち上げ、農業が楽しいものだと知ってもらえるよう様々な挑戦を続けてきました。
閑散期にできることを
25歳の時に高山市漆垣内(うるしがいと)地区の専業農家に嫁ぎました。気づけばもうすぐ40年、ほうれん草を中心に、トマトや米の生産をしています。
高山は雪も多いので、嫁いだ当時は4月から11月が生産時期、そして12月~3月は農閑期でした。農閑期にはパートに出る人も多いが、この時期は農業関係の研修会も度々あって仕事を休まなければならないため、何か良い解決策はないかと考えていました。
そんな時、岐阜県の農業女性の大会に参加し、農産物加工の盛んな美濃の方のお話を聞きました。そこで「グループで農産物加工を始めるのは難しくない。加工には調理師などの資格もいらない。」ということを知り、「そうか、自分たちの都合に合わせて出来ることを始めればいいんだ!」と気づきました。帰るときにはワクワクして、誰にどう相談しようかと考え始めていました。
早速、地域の婦人部の中で料理の得意な人や食品の店に勤めていた人に相談をし、市役所の農務課、県の農業改良普及センター、地元の農業委員の方などの関係機関に思いを伝えに行きました。当時は女性の活動に注目が集まりだした時期で、すんなりと協力しましょうという返事をいただくことができました。そして、地域でやる気のある農業女性に声をかけ「飛騨高山うるっこ」は始まりました。1998年のことでした。
何を作って誰に売るか
「うるっこ」は「漆垣内」の「うる」、「ウルトラかーちゃん」の「うる」、「頑張って売るぞ!」の「うる」を取って名付けました。さて何を作ろうか。しかし、農繁期は忙しくて何もできません。そこで、冬に加工できるものをと考え、米と飛騨ならではの「えごま(あぶらえ)」で五平餅を作ることから始めました。市から「米の消費拡大の補助金」の話があり、商品化に向けて動き出しました。
最初は、大きさは?米の炊き方は?串はどこで調達する?製造場所と製造許可は?と、考えたり調べたりしなければいけないことの連続でした。決め手になるえごまのタレは試作を繰り返し、さらに誰が作っても同じ味になるようマニュアル作りも進めました。
試行錯誤を経て商品は出来上がり、農業祭などのイベントで販売すると「美味しい」「えごまが懐かしい」と、お客様からの嬉しい声をたくさんいただくことできました。これがやりがいの一つで、イベント出店は毎年続けています。しかし、販路開拓のために相談したお土産屋さんに「冬場は観光客が少ないから」と言われたため、「地元の人に買ってもらえるものを作ろう」と考えました。地元でよく食べられているえごまのタレだけを商品化したり、えごまのお菓子やトマトソースなど、ターゲットを考えて商品のラインナップを広げたりしていきました。また、「美味しければ買ってもらえるはず」と材料にこだわって商品開発をした結果、地元のスーパーのバイヤーさんから問い合わせをいただき、取引が始まりました。
加工所を作ろう
始めは地元の公民館で臨時の許可をもらって製造をしていましたが、続けるためには加工所が必要になってきました。メンバーは主婦ばかりで、なかなか大きなお金を出すことはできません。みんなで話し合い、活動を続けるためにと1年間積み立てをし、補助金も活用して2000年に加工所を作りました。
加工所で、みんなでわいわいと商品づくりをするのは本当に楽しい時間で、仕事ではあるものの、息抜きの場所にもなっています。農家の嫁ならではの悩みや思いも分かり合える仲間と楽しく、無理なく、長く続けていこうと活動してきました。
40代~60代の11人で立ち上げた「うるっこ」ですが、現在は60代~70代の8人になりました。ライフステージが変わる中で、高齢化や親の介護など参加が難しいメンバーも出てきましたが、楽しく、無理せずで続けています。
立ち上げから5~6年頃、イベント時には自分たちの商品のラインナップだけでは十分ではないことを感じ始めました。そこで飛騨地域の他のグループや生産者さんに声をかけ「ひだあねさの会」を立ち上げました。年に1回イベントを開催し、更に仲間が広がりました。現在は役員4名と約20人の担当者で運営していますが、こちらは近々若手にバトンタッチしていこうと思っています。
農業は楽しい!
息抜きは孫と遊ぶことや、主人とドライブに行き、その土地の美味しいものを食べることです。農家のいいところは自分でスケジュールの調整ができること。平日に休みも取れますし、天候など自然相手ではありますが、計画や目標を立てて達成していくことが楽しい仕事です。農業というと大変なイメージがありますが、今後は孫の世代が農業をやりたいと思えるような体制や仕組み作りをしていきたいと考えています。
数年前までは指導農業士もさせていただき、学生さんなどを受け入れていました。3日から長いと1か月、自宅に住み込みで仕事を覚えてもらいます。大変な仕事ではありましたが、後継者不足の農業の楽しさを1人でも多くの人に知ってもらえたらなと思っていました。特に農業女子にキラキラと活躍してほしいです。
座右の銘は「へこたれないぞ」。台風でほうれん草が全滅なんてこともありましたが、なんとか乗り越えてきました。「やりたいことがあればやる。後悔しない人生を」と思い、家業も会の活動もまだまだ楽しんでいこうと思っています。