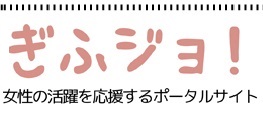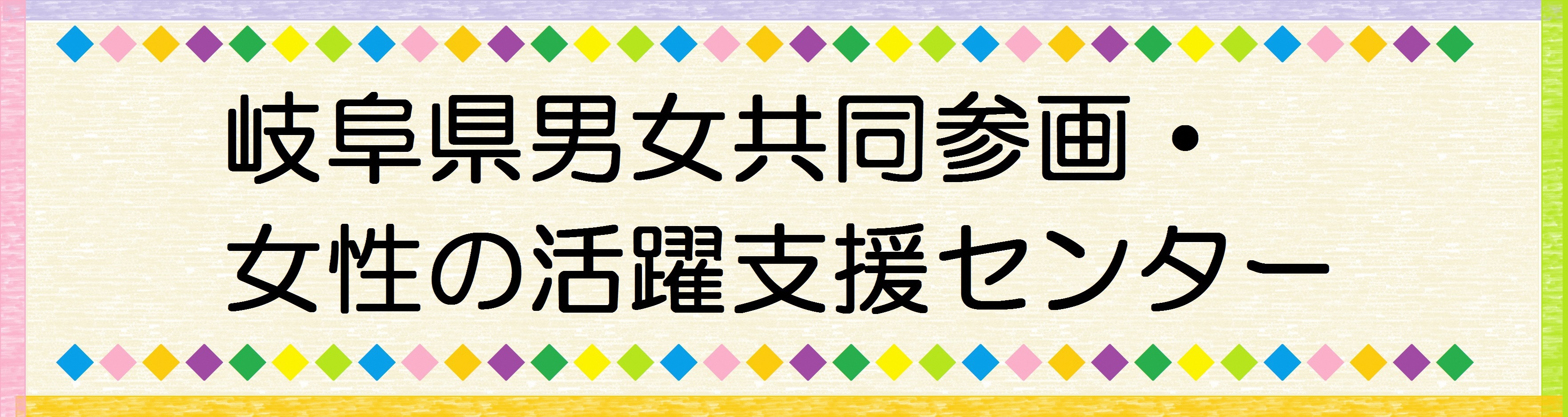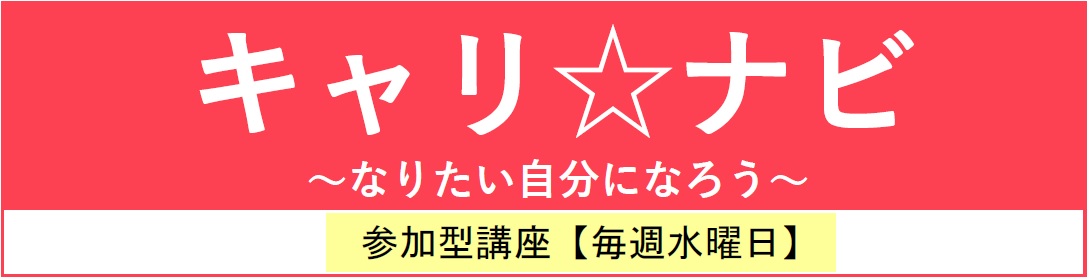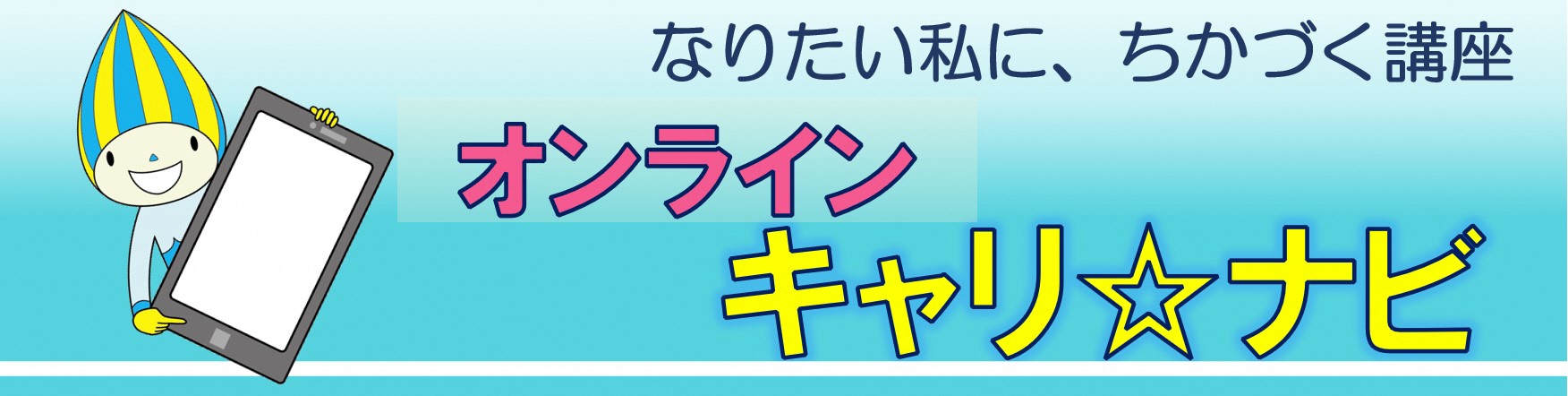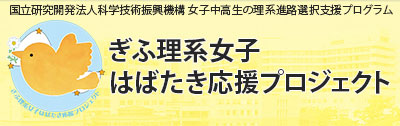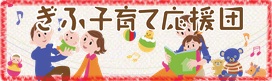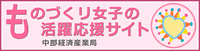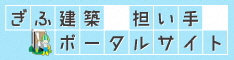渡辺酒造醸は、水の都と称される大垣市で1902年に創業。現在蔵を切り盛りする渡辺愛佐子さんは、3代目・進二さんの三女として1975年に出生しました。大学を卒業し山梨の修行先へ。その後、実家に戻り20代で杜氏となって今日まで日本酒づくりに尽力しています。なお、プライベートでは小学生の娘を育てる母親。時々、娘さんが酒づくりの仕事を手伝ってくれるようで、その姿が微笑ましいそうです。
髙3の時に後継を意識
家業で日本酒をつくっていると言われても、幼少期の自分には理解できていませんでした。というのも、かつての酒蔵は女人禁制。「危ないから入っちゃだめ」と言われていて、酒蔵には近寄れず、中で何が行われているかほとんど見たことがなかったからです。いつも「ここで何をしているのかな?」と疑問に思っていました。そんな自分が酒蔵で働くことを少し意識したのは高校3年生の時。父から初めて後継について話をされたのです。結果、東京農業大学で醸造を学ぶ道を選択。卒業した後は、山梨の酒蔵に就職し、酒づくりの基礎を学ばせていただきました。
20代半ばで実家に戻り、前任の杜氏さんのもとで渡辺酒造醸の酒づくりに取り組み始めました。当時、うちの蔵は自分たちの銘柄以外にも、桶売りといってほかの酒蔵からの依頼を受けて、その酒蔵が求める日本酒をつくっていました。今で言うところのOEMです。このため蔵全体の生産量が多く、仕込みのシーズンともなると、とても忙しい日々を過ごしていました。ところが、時代の移り変わりによって桶売りの商慣習が廃れていくと、蔵の生産量も減りました。
自分らしい日本酒を
杜氏になったのは、27歳の時。すでに酒蔵は女人禁制と言われる時代ではなく、ほかの蔵でも女性杜氏が活躍し始めていました。
日本酒の味は、杜氏の方針や指示によって大きく変わります。つまり杜氏とは、各蔵の酒づくりの責任者。でも杜氏になったばかりの私は、今までの蔵の味を自分で実現できるか不安でした。米の出来栄え、水の質、気温とそれによって大きく変わってくる麹の繁殖具合など、均一しない条件下では味を安定させるだけでも至難の業です。ましてやそこに自分らしさを表現する余裕は、新米杜氏の私にはありませんでした。ただ「いつか自分らしい、あるいは女性らしい日本酒をつくってみたい」との展望は、ぼんやりながら描いていました。
渡辺酒造醸には、「美濃錦」を筆頭に複数の銘柄があります。私が杜氏になって以降は、「あさちゃんのどぶろく」「覚眠森水酒」「清流の国」などがラインアップに加わりました。清流の国は、「県魚のアユに合うお酒を」という話が寄せられて、つくってみることに。アユの淡白で繊細な身と、ほんのり苦いワタとの相性を考えて醸し、清流を彷彿とさせる青い瓶に詰め、ラベルにはかわいらしい魚のイラストをあしらいました。また、もともとあった「白雪姫」という銘柄のラベルも女性らしさを感じるものにリ・デザインしました。
生酛への挑戦
2023年は、美濃錦の新たなラインとして「MINONISHIKI KIMOTO 純米無濾過 生原酒」などを発売しています。現在の日本酒は、人工の乳酸を使い、雑菌の繁殖を防ぎながらつくる「速嬢酛(そくじょうもと)」が主流ですが、「MINONISHIKI KIMOTO 純米無濾過 生原酒」については、速嬢酛ではなく、「生酛」でつくりました。生酛とは、蒸米に、水、麹、酵母を加え、蔵に住み着いた天然の乳酸菌の力を借りて酵母を培養することを意味し、これこそが昔ながらの伝統的な日本酒の製法なのです。速嬢酛に比べて、手間と時間がかかりますが、生酛ならではの味わいが楽しめるとあって、こだわっている蔵も多くあります。
今述べたように、生酛は天然の乳酸菌を生かした製法です。渡辺酒造醸は明治期から長く日本酒づくりを続けているので、天然の乳酸菌が蔵の中にしっかり住み着いています。つまり、生酛は歴史ある蔵だからこそ可能な製法とも言えるのです。そんな蔵で杜氏を務めているなら、やってみる価値はあると思いチャレンジしてみました。これからも「この蔵だからできる、私だからできる酒づくり」を念頭に置いて杜氏を務めていきたいです。
生酛の酒は、酸味が特徴的です。売り出した時は、やはり反応が気になるものですが、「シャープな酸味ではないので、飲みやすい」との意見を多くいただき、ホッとしました。ちなみに、酒づくりの繁忙期を終えると、時々イベントに出展し、消費者の皆さんと直接触れ合って、杜氏としての思いを伝えたりもしています。
杜氏であり母親である
娘が生まれたばかりの頃は、繁忙期ともなると毎日がとにかく目まぐるしくて、体力的な辛さを感じていました。そんな折、仕事中にケガをしてしまったのです。それを機に「働き方を見直した方がいい」と考え、一般企業と同じように8時から17時までを就業時間とし、休みもしっかり確保するようにしました。私は杜氏であり、母親でもあります。親子がコミュニケーションを交わす大切な時間を設けることで、心身ともに健康的になった思いです。
私自身、幼少期は蔵に入ったことはありませんでしたが、娘は自由に出入りしています。もちろん安全には配慮しています。時々娘に「これ手伝ってくれる?」と仕事を与えると、笑顔で取りかかるので、どうやら蔵の中で過ごす時間を楽しいと思ってくれているようです。実は自分の後継ぎのことは想像できていなかったのですが、最近「お母さんみたいにお酒をつくる仕事をしてみたい」と娘が言い出したので、その意思を尊重し、温かく見守っていこうと思っています。