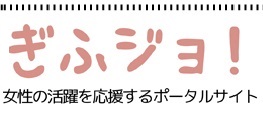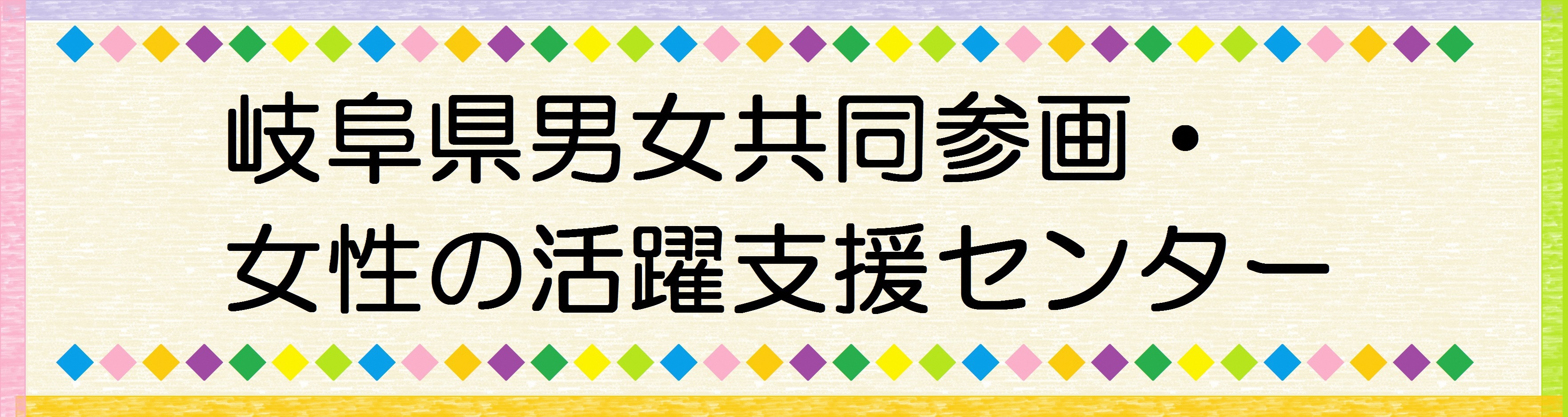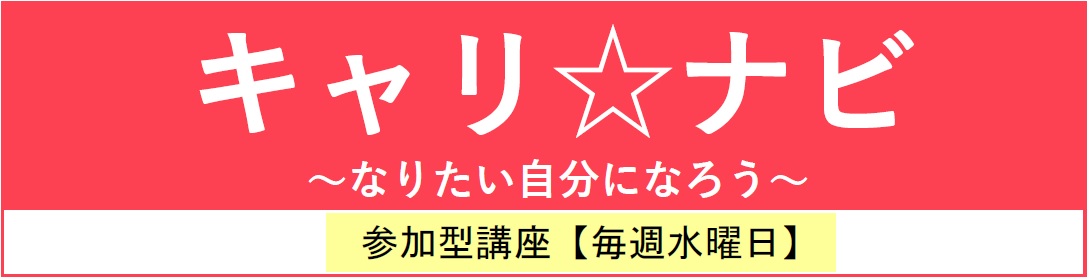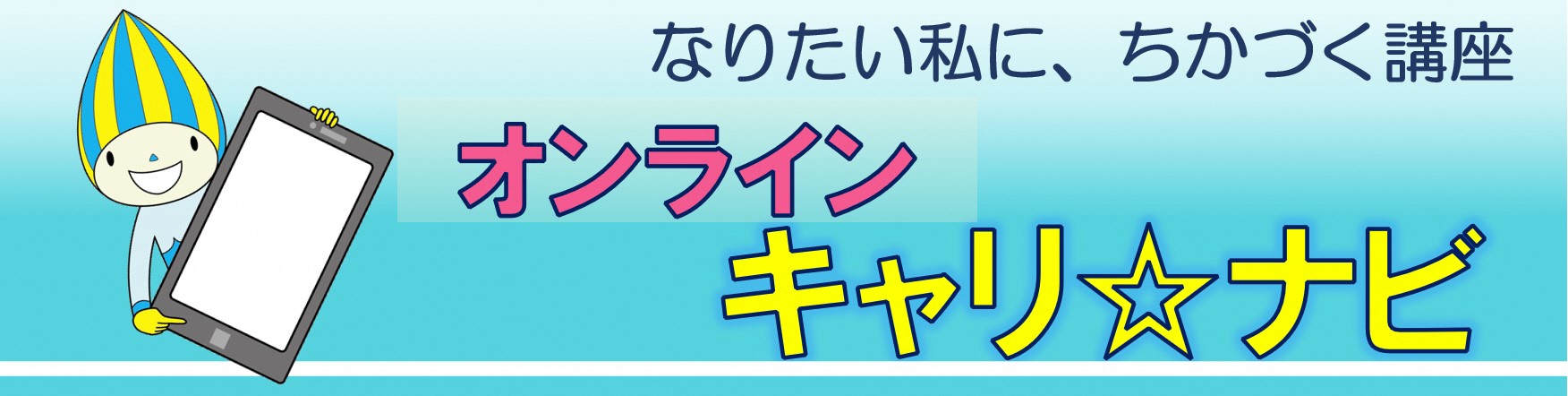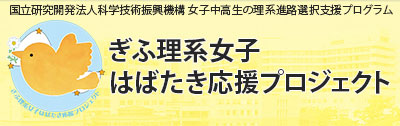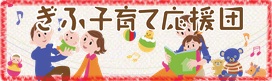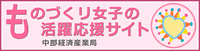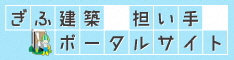「自然の中で働くって楽しそう」。そんなシンプルな動機で森林技術者を目指した松瀬乃亜さん。高校を卒業してから、美濃市にある岐阜県立森林文化アカデミーに入学。2年間の学びを経て、東濃ヒノキ白川市場協同組合に就職しました。チェンソーを巧みに使って木を伐倒する森林技術者は体力が求められる仕事ですが、笑顔を絶やさず毎日を楽しんでいる様子です。
強まる森林への想い
通っていた高校は農業系で、私は食品科学科に在籍。高校には森林科学科もあり、その学科に掲示されていた岐阜県立森林文化アカデミーという専修学校の生徒募集のポスターを見て「森林の勉強って、なんだか楽しそう」と思っていました。そんな日々が続くなか、森林への思いがどんどん強くなり、結果的にアカデミーに進学。これまでアウトドアタイプではなかった私ですが、校舎裏の演習林で木を切ったりする授業が新鮮に感じられて、充実した学生生活を送ることができました。
森や木に関わる生き方はさまざまですが、私は「山の中で木を切る仕事がしたい」と気持ちを固めていたので、卒業後はそういった仕事に携わらせてもらえる職場に入ることを強く望んでいました。
現在の勤務先となる東濃ヒノキ白川市場協同組合に入りたいと思ったきっかけは、インターンシップです。もともと組合では、伐採された木を受け入れて販売する市場業務を行っていたのですが、2019年から新たに林産部を発足。その結果、自分たちでも伐採をするようになったので、私は「ここならやりたいことができる」と感じました。また、若いメンバーばかりの部署だったことも決め手のひとつに。同世代なら仕事中にコミュニケーションが取りやすいと思いました。実際、仕事中は和気あいあい。先輩とも冗談を言い合える仲です。
伐倒技術を磨く日々
伐倒は単純な作業に思われるかもしれませんが、とても奥深い。まずは、作業前に切るべき木を選別し、伐倒後にスムーズな運び出しができることを考慮した上でどの方向に切り倒すかをきちんと見極めなければなりません。
いざ切る時は、最初に「受け口」をつくります。受け口とは、チェンソーの刃を水平と斜めに入れることでつくられた切り口のことで、「く」の字のような形です。木は受け口のできた方向に倒れます。言い換えると、受け口を正確につくれないと、狙った方向に木は倒れてくれない。続いて、「追い口」をつくります。追い口とは、受け口の反対側に入れられる直線的な切り込みのこと。追い口をつくることで、徐々に木が傾き始め、最後にくさびを打ち込むと倒れます。
周囲の安全に最大限配慮しながら、木の倒れる方向をうまく制御する。これが理想の伐倒です。就職したばかりの頃は、受け口や追い口がきれいにつくれず、なかなか狙った方向に木を倒せませんでした。上達するには経験を積むしかないので、来る日も来る日も伐倒を続けて技術を磨きました。おかげで作業スピードと正確性は高まったように思います。
現場では常に伐倒を担当しているわけではありません。伐倒した木の枝を払ったり切り揃えたりするプロセッサという重機の操作も担当します。重機操作も伐倒と同じで、奥深さを感じます。
仕事は常に体力勝負
仕事では重い荷物を持つのは当たり前。その状態で急な斜面を登ったり降りたりするので常に体力勝負です。仲間が手伝ってくれることもありますが、常に頼れる状況ばかりではありません。また、夏は空調服があるとはいえ、暑いです。山の中だから虫も出ます。こうしたことに理解を示さないと山の中で働けません。
大変な事ばかりではなく、良い事もたくさんあります。ひとつの現場の作業期間は数週間から数ヶ月間で、しばらくの間は同じ山に毎日入るのですが、「今日の気候は気持ちいい」「今日は鳥がたくさんいる」など、山は日々違った表情を見せてくれるので、新鮮な気持ちで仕事に取り組めます。最初の頃は、自然に囲まれたなかでお昼休みを満喫できることがうれしくて仕方なかったです。
最近、この仕事を選んでよかったと思うようになったことがあります。それは、デジタルデトックスが自然にできる点です。私たちが入る山の中は、登山客も来ないような場所なので、スマートフォンの電波は圏外。日中はスマートフォンを触ることができないため、デジタルデトックスが自然にできてしまうのです。ちなみに、髪とネイルの色は自由。実はおしゃれを楽しみながら取り組める仕事でもあります。
未来の後輩へ
今はまだ20代なので、しっかり休養すればすぐに体力は回復します。年齢を重ねていくと、体力的に厳しいと感じる場面がどんどん増えるでしょう。山を降りる日はいつかやってきます。もし山を降りることになったとしても、市場を持っているこの組合なら、そちらの業務に就くことができます。次のキャリアの見通しも立てられる職場なので、安心感は大きいです。
女性の森林技術者が少ないため、取材などで取り上げていただく機会がたびたびあります。私が森林技術者として奮闘している姿を広く伝えることで「おもしろそう」「ちょっとやってみたい」と興味を示す女性が増え、未来の後輩として組合に入ってきてくれるとうれしい。