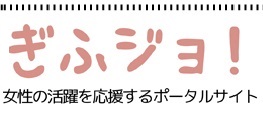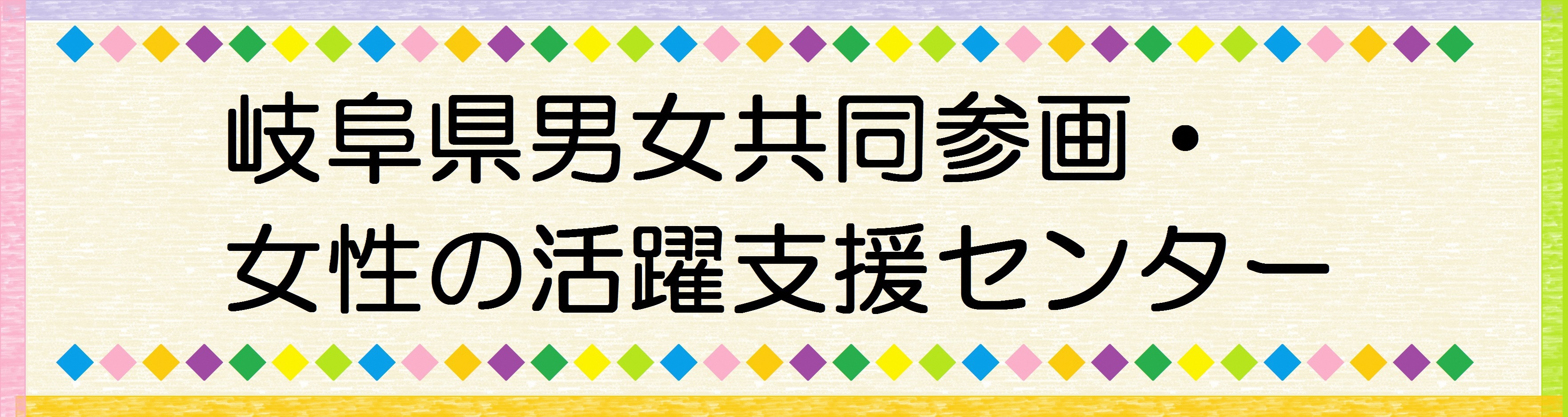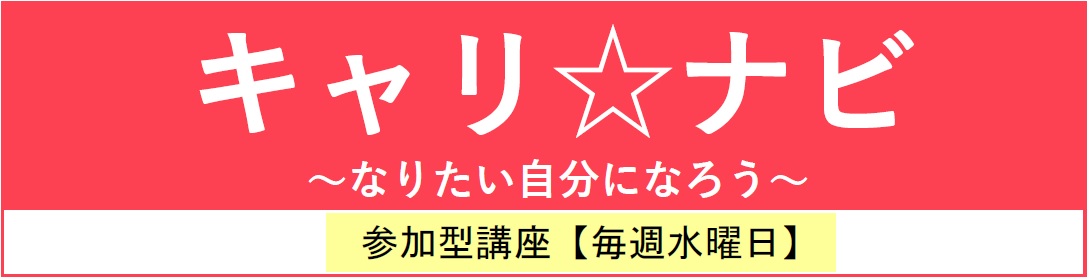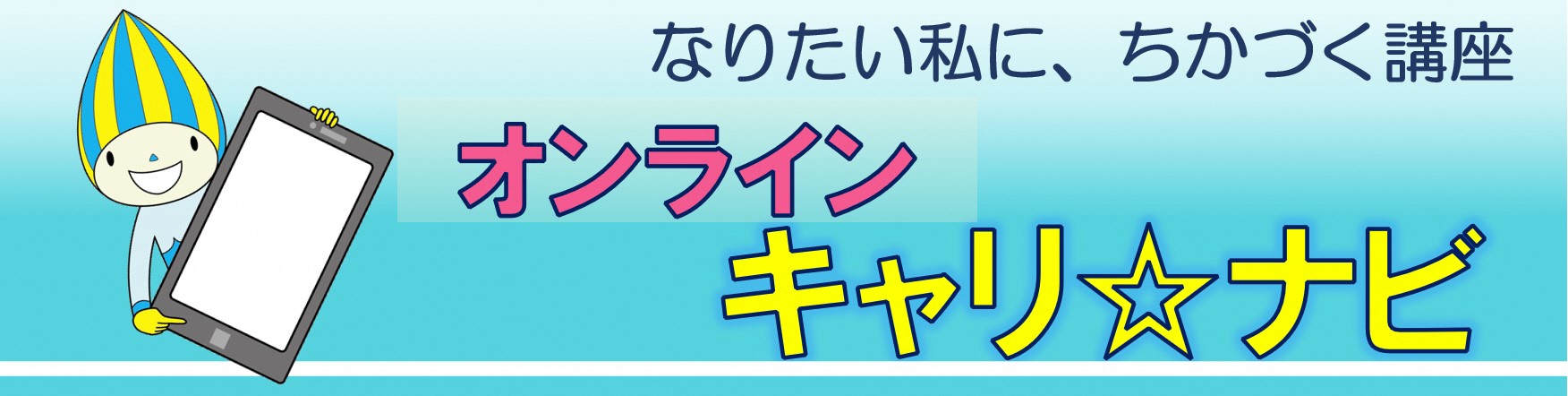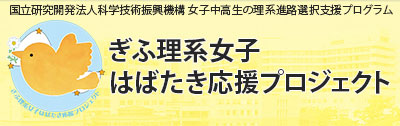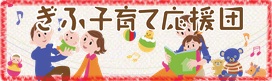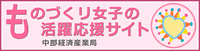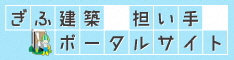瑞穂市の髙田住代さんは夫婦で鮎の養魚場を経営しています。養魚場は衛生管理の関係でご主人が担当し、住代さんは販売や出荷を行うかたわら、鮎のつかみ取り体験と鮎料理を提供するお店を営業。さらに養魚場の仕事と並行して県の女性農業経営アドバイザーや市の農業委員としても活動しています。
建築業から養殖へ
主人が子どもの頃、工務店を営んでいた義父が養魚場を始めたそうです。工務店で養魚池の建築を請け負い、面白そうだったので自分も養魚池を作り、副業にしたあと養殖一本に絞ったそうです。
私は住宅に興味があったので建築系の学校に進学し、卒業後に就職した会社で今の主人と知り合い結婚しました。主人も建築士として働いていましたが「実家は魚屋だ」と軽く言っていたので、鮎の養魚場だとは思ってもみませんでした。やがて義父母も高齢となって仕事がきつくなり、その様子を見て夫が建築会社を辞めて養魚場を継ぐことにしたので、私も夫を手伝うことになりました。
元気な鮎を育てるために
義父が始めた当初はニジマスやアマゴなども育てていましたが、その後、鮎一本にしたそうです。当時は琵琶湖産の稚魚を仕入れて育てていましたが、冷水病などの魚病の発生に頭を悩ませていました。鮎は魚体が小さくて弱いため病気になりやすく、さらに他の魚に比べて薬も非常に少ないので、病気が発生すると大変です。養魚場を継いだ主人は出来るだけ薬を使いたくなかったので、病気の出ない鮎の育て方を学びたいと思い、県の施設に行き勉強させて頂きました。
鮎の人工ふ化に取り組んで何年か試行錯誤を繰り返したのち、琵琶湖産の稚鮎など外部から鮎種苗を仕入れることを止め、自社で採卵し孵化させた人工種苗に切り替えました。飼育水は河川水から綺麗な地下水に切り替えて、無投薬に近い状態で鮎が育つようになりました。
鮎は感染対策を厳重にする必要があるので、養魚池はほとんど主人一人が担当しています。人工ふ化を始めてから30年以上休みなく、毎日鮎の飼育を昼も夜もやっている主人には頭が下がります。
養魚場の経営安定を求めて
鮎は夏が旬の一年魚で、一年一作です。以前は夏しか収入がなかったので、不作の年は生活が苦しかったのですが、今は秋に孵化した稚魚を育て、春先に他の養魚場さんへ鮎種苗として出荷したり、各漁協さんに放流用として出荷したりと、何回かに分けて収入があるようになり少しは安定するようになりました。電気代や餌代は毎年値上がりを続けていますし、自分たちも年を取り作業が辛くなってきたので、この頃は成魚の生産量を減らしています。
10年ほど前に養魚場の隣で「つかみ取り鮎料理」の店を始めました。小さな公園のように見えるためか、初めの頃はお弁当やハンバーガー持参でみえる家族連れに驚きました。駐車場も狭くて、ご近所の運送会社さんの駐車場をご厚意で使わせて頂く有り様で、なかなか採算が合わない状態が続いていましたが、数年前に水遊びコーナーを拡張し、駐車場も広げることが出来ました。お客様の口コミやSNSのおかげで、休日にはスタッフの手が回らないほど大勢のお客さまに来て頂けるようになりましたが、最近は私たちスタッフの高齢化と人手不足、夏の酷暑で綱渡り営業になっています。
それでも、つかみどり場で鮎を自分の手で捕まえた感触、自分でつかんだ鮎の塩焼きを食べた味や香りを子どもさんたちに覚えていてほしい、大人になって岐阜を離れてもお盆に集まる家族の笑顔とともに、自分の原風景として記憶にとどめていてくれたらと願って、毎年頑張って営業を続けています。
鮎を通じて地域の活動に参加
コロナ禍前は瑞穂市商工会の町ゼミにも参加しました。地元小学校の校外学習には20年ほど協力を続けていて、子どもたちに鮎のつかみ取りや鮎料理を体験してもらっています。その他にも岐阜県女性農業経営アドバイザーや瑞穂市農業委員のスタッフとして勉強会に参加させて頂くなど、鮎の養殖を通して得た知見を地域に還元できるよう活動を続けています。