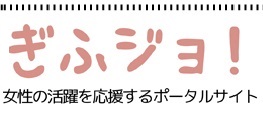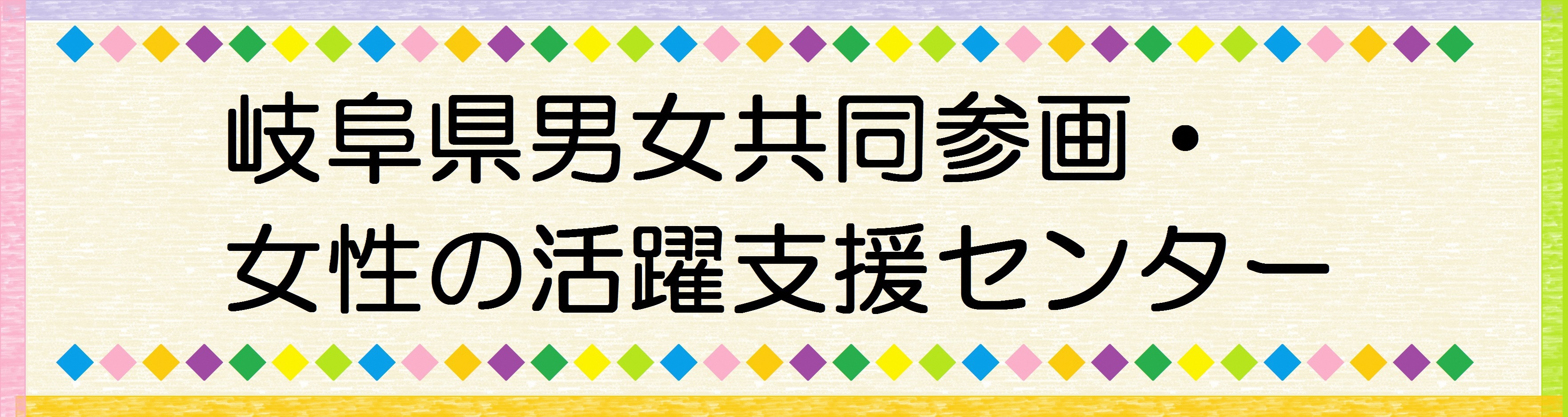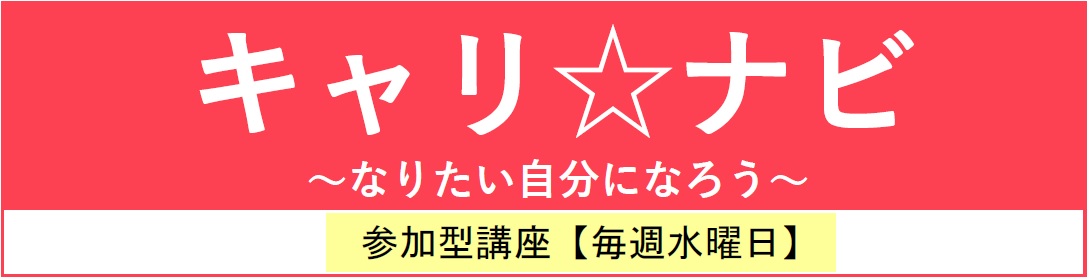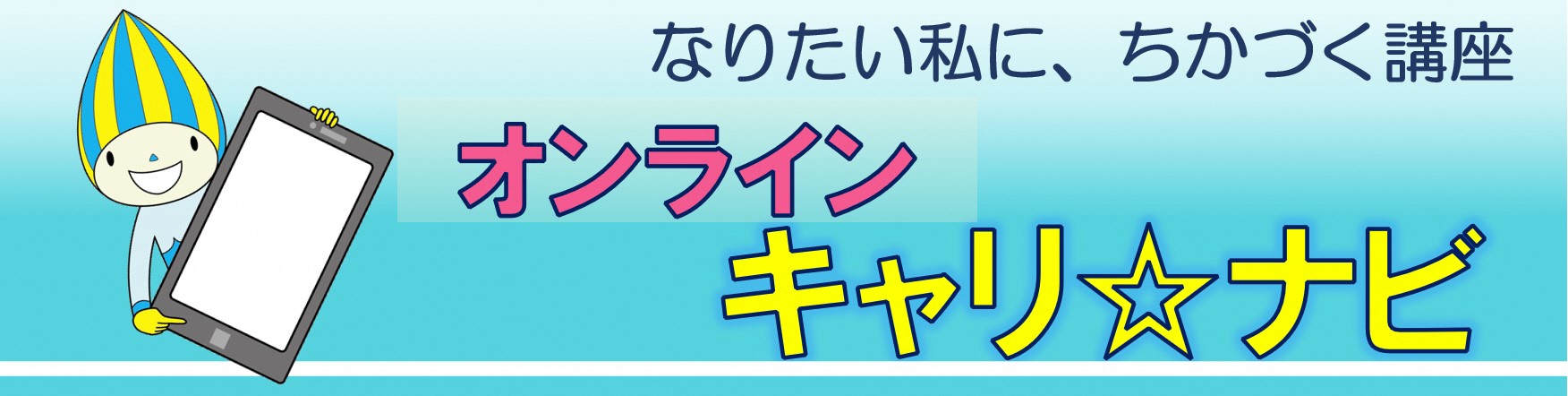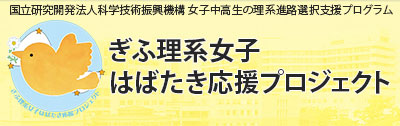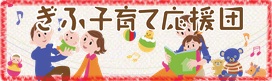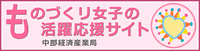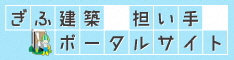竹内久美子さんは、長男が発達障がいの特性を持っていることから、その特性を活かした仕事に繋げられるような仕組みを作りたいと一念発起して木工会社を起業。障がい者の方々が仕事に生きがいを持ちながら、自立するための収入を得ることを目標に就労支援所を営んでいます。生きづらさを抱える方やその家族を対象とした交流会「ここまま」も毎月開催。関わる人が笑顔になれる場所づくりを目指しています。
起業のきっかけは息子
長男は1歳半検診の時に、自閉症スペクトラムの診断を受けました。現在に比べると、まだその特性や療育に関する制度が整っていない環境ではあったが先生方に恵まれ、学生時代は色々な経験を積むことが出来た。ところが就職となると、なかなか思うようにはいきません。転機となったのは、建設会社を経営している知人のところで住み込みで1年間働かせてもらったことです。本人の中で「今後も木に携わる仕事がしたい」という気持ちが芽生えたようで、そんな息子のバックアップのためにも木工に関わる就労支援所を立ち上げることを決意。まずは木工初心者でも作業しやすく木に携われるものは何だろうと考えていた時、木工旋盤の機械を扱う会社を紹介して頂きました。息子と見学に行き直接旋盤に触って「これだ!」と思いました。その後機械を購入し、作業所には廃業した木工工場の跡地を借りることにしました。そうして出来たのが「株式会社 紬葵」です。起業にあたっては良いご縁をたくさんいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
皆の意欲に応えたい
開業した時期がコロナ流行の時期と重なったため、ネット販売からスタートしました。最初に作った商品はボールペンです。皆様のご協力のもと、クラウドファンディングにも挑戦しました。「こんなもの作れる?」とたくさん声をかけてもらいながら、経験を積み技術を磨くことが出来ました。その経験を生かして、オーダーメイドの食器や、企業からの依頼で様々なパーツや製品を作ることができました。
木材はすべて県産材にこだわり、主に広葉樹を使用し、パッケージなどもオリジナルで考案し製作しています。現在は、私を含めスタッフは5人。基本的には営業・納品など外回りや経理などの事務、納期が迫っているときは工場に入ります。組み立てなどの内職もあるので、外出が難しいという方には内職の依頼をお願いしています。
また、月に一度、引きこもりなど生きづらさを抱える方とその家族、困りごとを抱えた方たちの交流会「ここまま」 も運営しています。同じ境遇や悩みを持つ人たちが集まり公民館でお茶会やワークショップを行っていますが、幅広い年代の方にご参加いただき、明るく前向きでにぎやかな会です。縁あって出会った人たちが継続して、モチベーションを持って働いたり、外に出るきっかけを持ったり、そういう場をつくるサポートをするのが役割と思っています。
支え導くことが使命
スタッフたちが安定して作れるものを模索する中、縁があり伝統工芸品のパーツの委託受注も頂きました。デザインから企画し、完成形に向けて試行錯誤を繰り返しみんなで考えながら形にしていくのでとても勉強になっています。私たちは伝統技術を手助けする立場ですが、スタッフの頑張りには本当に頭が下がる想いです。スタッフは感覚が長けた子が多く、努力を重ねるとどんどん精度が上がってきます。自分で開業を目指しているスタッフもおり、自立のために仕事以外の社会のルールやマナーや生活のことなども教えています。それぞれの得意なところを伸ばして、最大限に発揮できるよう導いていければと心がけています。人数が少ないからこそ、家族のような関係ですが、そんな中でも声のかけ方や仕事のペースの提案には細心の注意を払っています。
自分も周りも大切に
今は息子と小学生の娘、犬2匹と猫1匹と一緒に暮らしています。子どもたちふたりとも家事全般が得意。料理や洗濯も3人で分担して、助けてくれています。基本的に仕事は楽しく、あまり息抜き方法など意識はしていませんが、人と話すことは気分転換のひとつです。休日に子どもたちと、美味しいものを食べることが一番の楽しみです。
座右の銘は、スタッフにも伝え続けている言葉「自分の機嫌は自分でとる」。自分のコンディションを常に保つことは大事。自分が元気でないと人にも優しく出来ない、相手の気持ちになって考えられないと思います。お世話になった方から教えていただき、ずっと大切にしている言葉で、何をするにしても常に心に掲げています。
夢は、木工所を併設した福祉施設を建てること。雇用となると切実な話ですが、フルタイムは無理でも少しずつ働きたいという子もいます。その子たちを受け入れられるよう事業を大きくしていき、今頑張っているスタッフが自立して指導者になり、次に仲間入りする子たちに繋げていけるよう整えていくのが課題です。そして、1 人1 人の自立のお手伝いを今後も続けて社会参加する姿を見続けていきたい、一緒にみんなで大木になれるよう、毎年年輪を刻み確かな経験を重ねていけたら良いなと思っています。